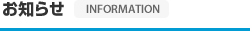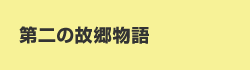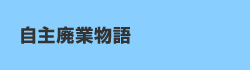夕食に家内が鍋をつくってくれた。野菜たっぷりの鍋。鳥肉のミートボール、豆腐、シイタケが入っている。やはりこの時期は鍋がうまい。いろいろな野菜から味がでるのか、スープも穏やかで、しかもさっぱりしていて美味しい。鍋を食べながら家内が、野菜も、人間も多様性があるからいいのじゃないかしら、と言う。確かにそうだと思う。野菜の場合は、例えば今晩の鍋の場合は、ダイコン、ホウレンソウ、ネギ、キャベツ、ニンジンなどが入っている。野菜の場合はまず味がぶつかり合うということはないのだろうが、人間の場合はぶつかり合いそうな時がある。それぞれ性格が異なり、得意、不得意もある。そのような人々が多様性を一つの味のようにするには、それなりのプロセス、努力が求められる。それがリーダーの役割の一番大事なところではないか。チームも組織も「人々の鍋」かもしれない。それはそれとして、わが家の場合は、武蔵野農園で収穫できる旬の野菜を材料にして鍋をつくる。今晩の鍋ではダイコンを半分使ったとのこと。これから冬に向けてホウレンソウ、コマツナ、シュンギク、ターツアイ、サトイモ、ニラなども鍋の材料になっていくことだろう。いろいろな多様性を楽しむことができそうだ。