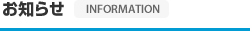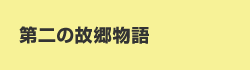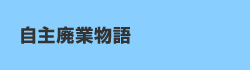話し方と聞き方は対をなしていると最近気付かされた。上手な話し手は良い聞き手であり、良い聞き手は上手な話し手になることができる。ところで話し方の教室はあるが、聞き方の教室というには寡聞にしてきいたことがない。最近「傾聴」の大切さが言われている。現代のような忙しい時代、私達は短い時間で自分の思っていること、考えていることを的確に相手に伝えることを求められている。そのための話し方のトレーニング、プレゼンの仕方を学んだりする。NHKEテレのテッドプレゼンテーションのプレゼンテーターの話しぶりにはいつも感心させられる。テレビに出演する前に、何度も練習しているのだろう。
以前アップルのジョブスのプレゼンの本を読んだことがある。ジョブズ流プレゼンの極意を書いた本だった。一方聞き方の本はまだ少ないようだ。話す方は能動的で、聞く(聴く)方は受動的だからだろうか。それで思い出すことがある。私の母がある病院に入院した時、院長の巡回の際、私の母は自分がずっと心の奥底にしまってきた思いをその院長先生に話した、ということがあった。今まで誰にも話さなかった心の中の問題だった。それを院長先生は優しく受け止めてくださった、と後で聞いた。この方なら自分の思いを受けとめ、理解してくださると母は思ったのだろう。