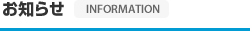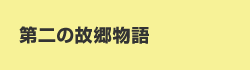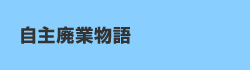今日は午後3時から「グリーンレジリエンスシンポジウム」(生態系保全×国土強靭化 次世代の自然資本活用の時代へ)に出席した。会場は三井住友海上保険株式会社の大会議室。
基調講演、特別講演の後、パネルディスカッションと続いた。主催は一般社団法人レジリエンスジャパン推進協議会。
今回のシンポジウムの趣旨は「我が国では自然資本を活用して防災・減災や地域創生に役立たせるという考え方が、ほとんど浸透していません。そこで当協議会では、自然が発揮する多面的な機能のポテンシャルを再発見・再認識し、それらを活用した防災・減災や地域創生に資するビジネスモデルを創発するため、「グリーンレジリエンス」のシンポジウムを開催し、様々な視点からの議論を致します」と書かれている。
講演の内容もパネルディスカッションの内容もそれぞれ充実していたように思う。印象に残った言葉がいくつかあったが、その中で2つほど上げてみたい。
1.ユニバーサルデザイン総合研究所所長の赤池氏は日本人の先祖の知恵から日本の国土に合ったレジリエンスの仕組みの可能性について触れていた。またこれからの時代は自然のメカニズムを社会に取り入れ、自然に回帰させていく社会になるとして「自然化社会」というコンセプトを提唱している。
2.パネルディスカッションでは三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社の図司氏が自然を資本として捉えるべきであり、大事にしなければ減少してしまうと指摘されていた。
現在私が取り組んでいる屋上菜園の活動もどこかで「グリーンレジリエンス」につながっていくかもしれない。そのためのビジネスモデルをデザインしていきたい。そのことも意識してこの大会議場の屋上にある屋上菜園で来年4月からの利用者への栽培指導に取り組んでいきたいと思わされた。