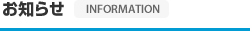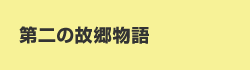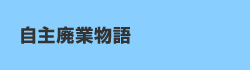若い頃、ドイツの哲学者ショーペンハウアーが読書について書いた文を読んだ。それがどんな時だったか思い出せないが、確か読書は人が考えたことの跡を辿る作業なので、あまり意味がないというような内容だった。そうか、そういう考え方もあるのだ、とその時はちょっと感心した。
跡を辿る作業が意味がないか、あるかは本に書かれた内容によるのではないかと私などは思うが、今迄いろいろな本を読んできたが、残念なことに、生来の記憶力の悪さもあり、今でも内容を憶えている本は少ない。本の読み方がそもそも雑読なので、文字情報が系統的に頭の中に入っていないこともあるだろう。長田弘が詩集の中で読書を「黄金の徒労」と表現していたが、まさに言い得て妙だ。
家内は「本ばかり読むと馬鹿になるわよ」とからかうが、私自身、最近嬉しいのは本がスラスラ読めることだ。従い読むスピードも早くなってきている。これは今迄読書を続けてきた効果なのだろうか。あるいは他に理由があるのだろうか。ということでいろいろな本を読んでみたい。今、特に読んでみたいのはやはり古典だ。当面は夏目漱石の小説と和辻哲郎の「風土」。そしてルカーチの「魂と形式」「小説の理論」。本棚の奥にしまわれたいたこの2冊の本を取り出し、薄っすらとたまったホコリを払って再読したい。何と言っていいか分からないが、青春時代の私にもう一度会って、現在の私が得ることのできるルカーチ理解を伝えることができれば、と思う。それは同時に自分自身のこれからの運命に立ち向かうための最後の情熱を取り戻す試みかもしれない。