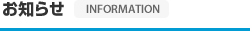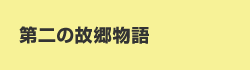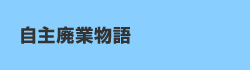現代の宗教の目的は何か。それを考えるために日本で宗教が果たしてきた役割・目的を振り返ってみると、以下のようなイメージが浮かび上がってくる。
飛鳥・奈良時代は「国家護持」。平安時代は「悟り」、末法思想が時代を覆った鎌倉時代以降は「救い」。この時代には法然の浄土宗、親鸞の浄土真宗、日蓮の日蓮宗の他、栄西の臨在宗、道元の曹洞宗が武士階級、庶民の間に広がっていった。戦乱も続き明日がどうなるとも分からない不安な日々。はかない命。人々は来世に救いを見出さざるを得なかった。
目を転じて、キリスト教も「救い」を当時の人々に伝えた。特にキリストが生まれ、育ったガリラヤ地方の住民はローマ帝国の支配と収奪、ヘロデ王による支配と収奪さらには宗教階級による収奪と律法による精神的圧迫と差別の下にいた。三重の圧迫に呻いていた。
宣教を開始したイエスは「神の国が近づいている」「救いがやってきた」という福音を伝えた。共観福音書と使徒の働きを読むと、すぐにでもこの世が終り、イエスキリストが使徒が生きている間に再臨し、この世が終る、という切迫感が伝わってくる。
しかし、末法によるこの世の終りも再臨によるこの世の終りも現実としてはなかった。
もちろん依然としてその状態が続いている、という説明もあるのだろうが、現代の人々はこの世を儚い仮の宿ではなく、真の故郷として、真に生きる場所として考えるようになっているのではないかと私には思える。
その意味でも今宗教に求められているのはあの世にむけての救いではなく、この世でより良く生きるためのこころの安らぎではないか。裁く閻魔大王、裁く父なる神ではなく、弱い私達に寄り添い、一緒にこの人生を歩いてくださる聖なる存在を私達は求めている。
金子みすずはこう詩に書いた。
私が寂しい時お母さんはやさいしいの
私が寂しい時仏さまも寂しいの