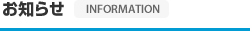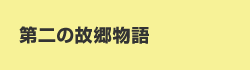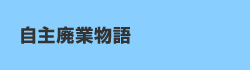涼しくなってきたので早寝早起きを再開したが、どうも朝食をとった後、眠気がやってくる。まるで食べ物の中に睡眠導入剤が入っているみたいだ。机に向かい仕事を始めようとするが、眠い。そんな時、ユーチューブで2曲聴いた。1つは杉本まさととKANAさんの「時間よ、止まれ」。もう一つはダンスの映像付きの「大阪ボレロ」。2曲ともテンポがいいし、キレがある。好きな曲だ。少し眠気が飛んだ。窓を開けて外気を入れる。雨空が見える。
半農半X人としては朝飯前に早朝農作業をしたいのだが、今朝は雨が降ってきたので、残念ながら中止。この埋め合わせはどこでできるかな。夜明けの時は晴れていたのに。大気が不安定だ。
ということでこれからの時間は江戸人を見習って昼過ぎ迄「稼ぎ」の仕事をしよう。いろいろな連絡業務もあるけど、今朝は「エゴマ栽培による耕作放棄地活用」のビジネスモデルのデザインに取り組む。完成まで2週間はかかるだろう。2週間かけてプロジェクトのプロトタイピングをつくる。その上で関係者と打ち合わせに入る。
午後は出かけて外国人ジャーナリストからの屋上菜園についての取材依頼の段取り。取材先への説明と取材許可を取る。これは「務め」ということになるだろう。
それでは遊び、娯楽は?人生をもっと楽しまなくっちゃと思うが、江戸人のようにおカネをかけずに楽しめる娯楽を持ちたいものだ。
今日は「務め」の後、谷根千(谷中、根岸、千駄木)辺りを徘徊しようか。俳句、時代小説のネタ探しを兼ねて。