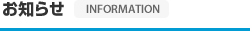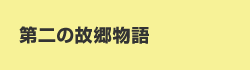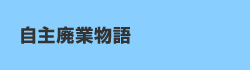日本経済新聞土曜日の夕刊文化で茨木のり子さんの詩「根府川の海」が取り上げられていた。「アッ」と声を上げた。私は学生時代、詩を書いていた。と言っても妄想の産物のようなもので詩と言えるようなものではなかったが、それがキッカケになって何冊かの詩集を読んだ。最初は思想詩のようなものを好んだが、途中から詩の持つ深い世界に関心を持つようになった。私が青春時代の、いわば吹き溜まりで読んだ2人の詩人の作品が私に深い衝撃を与えた。
1人は村上昭夫の「動物哀歌」、もう一人は茨木のり子の「対話」「見えない配達夫」だった。当時の私は人生の重心を持とうとしても持てず「生きているという実感に乏しい生活」をしていた。当時流行った言葉で言えばデラシネ。デカダンス風だったのかもしれない。
茨木さんの「根府川の海」に見え隠れする女性の凛とした心意気に惹かれ、ある日茨木さんが何を見ていたのか、知りたくて、そのためだけに東海道線に乗って、根府川駅までやってきた。今風に言えば「男前の詩」。いや男以上の詩かもしれない。プラットフォームには確かカンナが咲いていたと思うが、どうも記憶が定かではない。駅の改札を出て、石ころだらけの崖を降りて根府川の海に触れた。両手で波を掬って唇を濡らした。暫く青い太平洋を見ていた。
茨木さんは戦時中、愛知県の実家と学校がある東京の間を往復する時、根府川駅を何度も通過していた。
私は弟が入院している伊豆長岡の病院に行くために何度も根府川駅を通過した。今ではカンナよりもパノラマのように眼前に広がる青い海が好きだ。根府川駅を通過する度に私は席を立って、ドアの傍に行き、海を見つめる。「根府川の海よ」