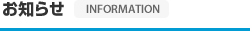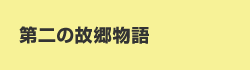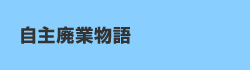最近アルゴリズムという言葉をしばしば耳にする。以前NHK EテレのTAD プレゼンテーションでクリストファー・スタイナーがアルゴリズムが株式市場を支配し、そしてあらゆるところにアルゴリズムが拡がっている様を説明していた。以前人工知能の会社の営業面の手伝いをしていた時、アルゴリズムという概念に初めて出合った。一つの結論を出すための複雑なプログラム、という程度の理解しかなかったが、スタイナーのプレゼンを見て「本当のところはどんなものなのか」知りたくなり、幸いスタイナーの書いた本が出ているので、早速購入した。(2013年10月10日初版)
「アルゴリズムが世界を支配する」(角川選書)だ。帯には「未来はアルゴリズムから逃れられない‐ボットに支配される社会で成功する道はどこにあるか」
一読して感じたことは私達が知らない間に、知らないところでアルゴリズムが拡がり、浸透している、という驚きと、同時に不安だった。夥しい数のアルゴリズムがまるで生き物のように動いている。アルゴリズム同士がぶつかり合って飛んでもないことが起こる。
2010年5月6日の米国の株式市場の考えられないような株価の破滅的下落と反発回復はトレーダーが手洗いやコーヒーを買うために数分席をはずしていた間に起った。
アルゴリズムの存在がなければ、マーケットはこれほど早く、これほど激しく乱高下することはなかった。ウオールストリートを襲った有名な「フラッシュクラッシュ」事件だ。
「アルゴリズム自体は理想的な成果を上げるために機械的に発せられる一連の指図だ」(同書92p)であるにも拘らずなぜこのような理想的とも言えない結果をもたらすのだろうか。私には個々のアルゴリズムとアルゴリズムの間の関係性調整のアルゴリズムが欠如しているからと思えるが、果たして関係性調整のアルゴリズムなどというものが可能なのだろうかという疑問も同時に湧いてくる。恐らくアルゴリズムの世界を支配しているのは「弱肉強食」、あるいは「自然淘汰」の不文律なのかもしれない。ある意味で極めて野蛮な世界だ。
一方野菜も含め植物と接していると植物の世界にもアルゴリズムがあるのではないかと思わされる。小さな種が、土中温度、湿度、太陽光、土の化学性、物理性、生物性などの情報を独自のセンサーシステムで感知しながら根を伸ばし、発芽していく。葉をつける野菜、実をつける野菜、根を食べる野菜へと生長していく。
現代人は人間が作った人工物としてのコンピュータのアルゴリズムの世界だけでなく、自然のアルゴリズムを理解して、より良い社会を、世界をつくっていかなければならないという、今だかつて経験したことのない複雑で、壮大な世界で生きていくことを求められているようだ。
なおアルゴリズムという用語は9世紀のペルシャの数学者、アブー=アブドウラ・ムハンマド・イブン=アル=フワーリズミーから来ているとのことだ。彼の名前が「アルゴリズム」と訳され、それがそのままシステマチック/オートマチックな計算手法を指すようになっていった。(同書93P)