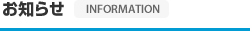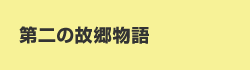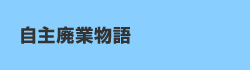有機野菜、有機栽培という言葉を使う時、私はそのために労苦された人々の言葉を思い起こす。小川町の有機野菜塾に通った時、金子美登さんが有機農業に切り替えることを決断し、実行に移そうとした時、集落の農家から強い反対を受けた。この反対が金子さんにとってどれほど厳しいものであったか、都会で暮らしていた者には想像がつかないものであったと思う。金子さんは「変り者扱い」された。ところが金子さんをチャンスを与えてくれた人がいた。金子さんの信念に動かされたに違いない。
そして今日金子さんの下里は天皇皇后両陛下が訪問されるまでに有機農業では著名な集落になっている。
今朝、昨日買った星さんと山下さんの対談集「農は輝ける」を読んでいた時、星さんが山形県で有機農業に取り組んだ時、国が推進する近代化に対抗する動きと地域社会から見られ、大変な圧力を受けたこと、歯を食いしばってそれに耐え続けたことを述懐されていた。
そこには自分自身との闘いもあった、と。恐らく自分自身との闘いが一番厳しかったのではないだろうか。星さんの話の後、有機農業とは一定の距離をとった山下さんが「有機農業とはまさに勇気農業」と言われている。
私達市民の農業で、有機栽培とか有機農業という場合、先人の闘いと労苦をいつも頭の片隅においておきたい。単なるキャッチフレーズにしてはいけない。
日本農政の「近代化」推進に対して、「それは違う」と異論を唱え、孤立を恐れないで有機農業に取り組んできた先人の足跡を辿りたいと思う。有機ある農業者に、私達市民、消費者は何をもって応えていったら良いのか。