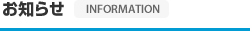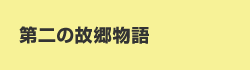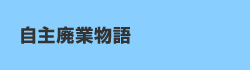最近友人のK君が「今さえ良ければいい」と言うのを聞いた。彼はそんな刹那主義的なことを言う男ではなかった。いつも将来のことを考え、計画的に物事を進めるタイプと私は見ていたので、「アレッ?」と思って彼に尋ねた。
私「『今さえ良ければいい』というのはどういうこと?」
K「70歳を過ぎた頃から、そう思うようになった。友人、知人が周囲で次々と亡くなっていく。最近迄元気だった奴までがある日突然幽明境を異にする。人生の儚さを感じるね。僕もある日突然ということがリアリティを持ち始めたんだ」
私「確かに僕たちの齢頃になるとそうだ。訃報に接すると、まだ若いのに、と思う」
K「訃報が段々増えてくる。ところでキミは自分のことをどんな風に考えている?」
私「僕は随分勝手な考えかもしれないが、自分は長生きしなければいけない、と思っている。僕を可愛がってくれた海外駐在時代の上司2人が60代台前半で亡くなっているし。それに・・・」
K「そういえばキミの場合は別の理由もあったね。」
私「そうなんだ。・・・まあ自分のことはとにかくとして、話を元に戻すとK君は『今さえ良ければいい』と思うようになって、自分の中で何か変ったことがある?」
K「僕の場合、『今さえ良ければいい』というのは刹那主義ではないんだ。今を大切に、丁寧に生きたい、それに自分の欲望といってはなんだけれど、やっぱりやってみたいことは余り我慢せずにやってみたい。将来のことを心配してもキリがないし、そのために心身のエネルギーを消耗したくない。エネルギーの備蓄も限りがあることだし。そうそう最近思うところがあってエンディングノートを書いた。書き終わった後、自分の人生はこんなものだったんだと思った。こんな風にしか生きられなかった、と。でもそれでも生き抜いてきた。・・・自分を労い、褒めてあげたい気持ちもどこかにある」
私「僕もエンディングノートをつけ初めている。過去は事実だ。でも未来はどうなるか、分からない。最近僕はやっと自分らしい人生を生きている、と感じている。もっと早くそんな境地になれたら良かったんだろうが、それも自分の器量だと思う。大器ではないが、晩成型なんだろうな。小器でも晩成のチャンスはあると思いたい」
K「そういえば最近のキミを見ているともう一度「青春」をしているようだ」
私「ありがとう。そう見ていてくれるのは嬉しいね。これからの3年間が自分の人生の中で2回目の青春時代だと感じているんだ。悲しいことがあっても辛いことがあっても心の真ん中でワクワクしていられる、そういう月日を持ちたいね」
K「第二の青春は賞味期限が3年間?そういう気持はこの齢にならないと出てこない人生の
「コク」のようなものかもしれないね。「キレ」はもう無いけど。僕が言う「今さえ良ければいい」というのは「今が良ければいい」いや「今を最高の時にする」と言い換えた方がいいようだ」
私「平凡でも人生の味、大人の味がやっと分ってきた・・・と言ったら言い過ぎかな」
K「いいね~。お楽しみはこれからだ、と言うフレーズがあるけど、お楽しみは今だ、でいこうか」
私「お楽しみは今だ、前向きの刹那主義、万歳・・・だね」
私とK君は飯田橋のガード下の行き付けの居酒屋で思わず祝杯を上げた。「我らの人生に祝福あれ!」
若い店主が「お2人とも元気ですね」。にっこり笑って声をかけてくれた。