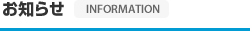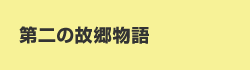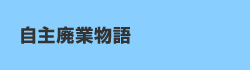二人で話す時と三人で話す時は心構えを変える必要がありそうだ。二人で話す時は相手のリズム、ペースに合わせて話をすれば良いのだが、三人の場合は事情が違ってくる。つまり3人が同時に話すことができないので、A とBが話している間、Cは二人の会話を聞いていなければならない。Cは話を聞きながら、自分の言いたいことをAとBとの会話の流れを見ながら、タイミングを選んで、Aと話したり、Bと話したりする。三人の場合、話の流れというか本筋を三人が共有している必要があるが、通常の日常会話の場合、誰が話の主導権を取るか、という問題が出てくる。つまりどこかで競争意識も生まれてくる。三人が均等に話すチャンスを分け合うことができれば良いのだが、現実問題としてそれができず、AとBとの会話が中心になり、Cは聞き手という役割分担ができることもある。雑談的な立ち話などであれば、そう問題にはならないだろうが、ビジネスミーティングなどの場合はA、B、Cの誰かが話しながら調整する必要が出てくるのではないか。また会話の主導権を無意識の内に取ろうとして発言内容が大袈裟になる場合もありそうだ。普段何気なく話しているが、三人で会話をする時に上記の問題を想起することによって、楽しい三人の会話にしてみたらどうだろうか。