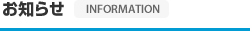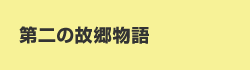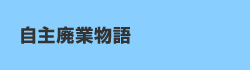東京の30年後 高齢者5割増、一方増え続ける空き家
国土交通省は「首都圏白書」で2040年時点の東京圏の生産年齢人口(15~64歳)が10年に比べて23%(550万人)減少、高齢者人口は5割増との見通しを示した。このまま行ったら、東京圏は高齢者が目立つ活気の乏しい都市圏になっていく。労働生産性だけでなく、新しい知の創造の面でも残念だが、低下の一途を辿ることになるだろう。
このような見通しを劇的に変えるシナリオはないものだろうか。答えは一つ、ではないだろうか。若者が意欲と希望をもって働くことができ、通勤にも時間がかからず、家賃が安い、物価も安いというようにしたら、若者は東京に集まってくるのではないか。但し問題はそう簡単ではないようだ。まず若者の多くは非正規労働者であり、低所得者である。ニートもいる。従い、住宅弱者になりやすい。その結果、劣悪な住環境の中で暮らすことになる。現在の日本では再就職、ステップアップのための公的な職業訓練というセフティーネットも不十分と言わざるを得ない。従い、現状の仕事環境からなかなか抜け出すことができない。その結果年金を受給している高齢者とその原資を負担している若い人達の間で一種の対立感情がうまれている。若者が将来に希望を持てない国にした責任の一端は私達高齢者にもある。世の中の矛盾を組み合わせ、オセロゲームのように一挙に黒を白に変える方法はないものだろうか。そのことを考えなければならない日本になっている。空室は54万4800戸に増えている。しかし住宅弱者にはまともに住む家がない。高齢者は増える一方だが、介護施設は圧倒的に少ない。いずれ高齢者の多くが介護弱者になる可能性が大きい。東京23区の一部で施設定員数/利用者数は25%切っている。これから鉄道を始めとした都市インフラについても根本的な見直しが迫られ、また社会の地殻変動も起こっていくことだろう。その変動を少しでも良い方向にもっていくために、日本型ビジネスモデルに寄せられる期待は少なくないものと考えている。